救急医になった理由④ 【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】
第1章 こちら救命救急センター
救急医になった理由④
本州最北端の三方を海に囲まれた大間町の国民健康保険大間病院は、日本でも有数のへき地病院として完結型の治療を行い、救急のモデル病院でもあった。明秀は副院長として自治医大の同級生である官川副院長(内科と小児科)とともに二年間勤務した。明秀が着任するまでの大間病院は、まともな人工呼吸器が一台もなく、また外科医がいないときなど、患者の疾病が重症化した場合の対応がむずかしかった。たとえば心筋梗塞の場合、キリップ分類”四”の患者は全員死亡していた(キリップ分類の一は軽症、二、三、四と重症になる)。心筋梗塞は発症してから三時間以内にカテーテルの手術をすべきだといわれていたが、大間病院ではその特殊な手術をすることはできない。救急車を走らせて一時間でむつ総合病院、三時間で県立中央病院、あるいはフェリーに乗って九十分で函館の病院もあったが、重症患者を搬送することは不可能だった。キリップ分類”四”の心筋梗塞の死亡率は、東京都内では一桁でも大間町では通用しなかったのである。 腎不全の患者の場合は、人工呼吸器をつけ透析の治療もしなければならない。当時は透析の器械がなく、集中治療のほうで出始めていた血液濾過透析をした。普通はポンプを回して静脈に針を刺し血液を抜き、きれいにした血液を静脈に戻すのだが、大間で行った血液濾過透析は動脈に針を刺し血液をフィルターに通してきれいにしてからを静脈に戻すという方法だ。動脈と静脈の圧の差でフィルターを通すのでポンプは必要なかった。これで大掛かりな装置がなくても何人かの腎不全の患者が助かっている。 明秀は人工呼吸器の新型四台とペースメーカーの導入、開胸手術の設備、透析室の準備も始めた。大間病院は新しい病院だったが、軌道に乗ってくると患者数も増え、胆石や胃がんの手術も行うようになり年間の手術件数は一〇〇件を超えた。この小さな病院で百件というのはたいへんな数字で、それだけ町民に信頼されるようになったということだ。 「当初は内科、外科、訪問診療、在宅、検診、いろいろな問題が山積みされていましたが、努力すればたいていのことは解決できました。また、町の一員として地元の人たちとの交流も多かった」 明秀は大間町に来てから日本救急医学会で論文を発表してきたが、心臓カテーテルのことなどわからないことがあれば積極的に質問し、学会で得た知識を大間病院に持ち帰って実践することができた。 当時、日本救急医学会ではへき地の救急医療が取沙汰されたが、それまでは見向きもされなかったのである。シンポジウムの演題として明秀が提出した論文、「本州最北端の救急医療」が採用になり、スピーチをした。また、翌年のフオーラムセッションでは四十分のスピーチをして注目された。そのころから明秀は救急医学会とのつながりができ、へき地にも救急が必要であると痛感したのである。次回に続きます…
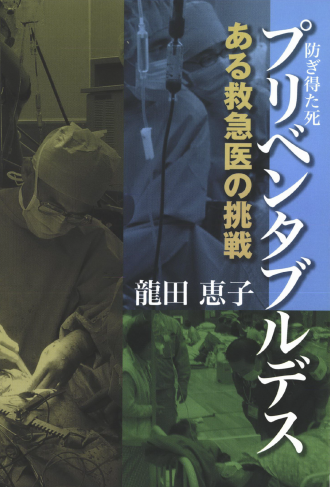 本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。
なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。
本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。
なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。
早く続きを読みたい、書籍で読みたいという方は http://www.cbr-pub.com/book/003.htmlや Amazonから購入できます。
◁過去の記事: 救急医になった理由③ 【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】
▷新しい記事: 救急医になった理由⑤ 【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】
