救命救急センターは社会の縮図① 【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】
第1章 こちら救命救急センター
救命救急センターは社会の縮図①
“病院は人生の縮図である”ということをよく耳にする。私自身もそれを実感させられたのは、やはり家族や親しい人たちが病に倒れて看病に当たり、さらに自分の入院体験を通してである。そこは患者それぞれの背景や死生観が浮き彫りにされる場でもある。 二十四時間体制の救命救急センターには、実にさまざまな救急患者が搬送されてくる。赤ん坊から高齢者まで職業もいろいろ、リッチマンとプアマン、医師のいうことを聞かない患者と素直な患者。見事なほど、患者の性格が表面化してくるのも、社会の歪みが浮き彫りにされるのも救命救急センターなのである。 川国市立医療センター救命救急センターには年間約一七〇〇人の入院患者数があり、そのうち約半数が集中治療を要する患者である。今明秀が救命の現場で見た〈生と死の境界線〉、一刻を争う状況の中で「なんとか助けたい」の一心が患者のかすかな命に力を注ぐ。なぜ、患者はここに来たのか。救われた命のその先には何があるのか。さまざまな患者の人生が垣間見えてくるとき、明秀の胸に去来するものとは何か。 ある四月の雨の朝、東北道を運転する二十九歳の女性の車がスリップして横転、彼女は車両の下敷きになり、重篤な状態で救命救急センターに搬送されてきた。脳震盪、両足の大腿骨骨折、首の骨折、動静脈断裂、内臓破裂。緊急手術後も三回の手術が行われた。多くの重症患者の命を救ってきた明秀は言う。 「平常心で運転に集中していたらあんな事故は起きない。あれだけのけがをしたのには、やはり原因があるのです」確かに雨の日は道路もスリップしやすいが、スピードを出さずに運転していればいくらでも防げる事故だったのかもしれない。あとで、明秀が患者から聞いた話では事故前は失恋したばかりのうつ状態にあったという。患者の私生活について医師としてどこまで関与できるのか、あるいは治療に専念することが医師の役目だとしても、患者や家族の回から飛びだす本音の言葉には貴重なヒントが隠されている場合もある。固く口を閉ざしていた患者でも「ああ、このお医者さんには聞いてもらいたい」などと思うのか、ポツリポツリと話し始めることもあるだろう。彼女の失恋が事故を引き起こした直接の原因ではないにしても、生活環境が精神に与える影響が大きいのと同じように、車の運転にはそのときの精神状態が作用するものである。結果、彼女は車の事故で重傷を負った。 入院中の彼女は術後の自分の姿を悲観し、将来を憂い、PTSD(外傷後心的ストレス)に見舞われたが、七月にはどうにか独りで歩いて退院した。 医師は患者のけがや病気を治すことはできても、生活環境を改善することはできない。彼女の場合、もし失恋していなければあんなにひどい事故には合わなかったかもしれないし、それはなんともいえない。命はとりとめたものの入院中は事故による傷や開腹手術の縫合跡など、以前の自分の姿とは違っているわけだから、当然、落ち込むだろう。生きていたくないとも思うだろう。しかし、死ななくてよかったと心から喜ぶ親しい人たちの顔を見たとき、ようやく生を実感できるものなのかもしれない。ちょうど年齢的にも三十代に差しかかろうとしているときに大波にさらわれ、心身ともに傷ついた彼女がその後の人生をどう生きていくかは彼女自身の心が決めていくことなのである。 現在、彼女は郷里で水泳のインストラクターをして元気で落ち着いた生活をしていると聞く。次回に続きます…
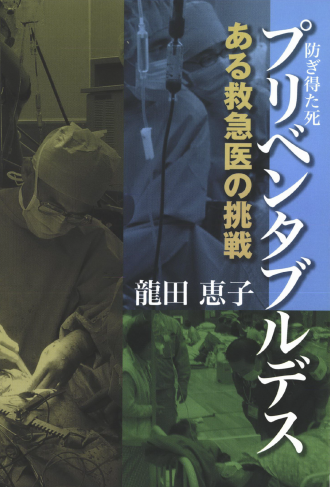 本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。
なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。
本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。
なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。
早く続きを読みたい、書籍で読みたいという方は http://www.cbr-pub.com/book/003.htmlや Amazonから購入できます。
