八戸市立市民病院救命救急センター⑤【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】
第3章 救急こそ医療の原点
八戸市立市民病院救命救急センター⑤
三戸郡倉石村は、いまでこそ温泉や果樹園、「ふれあい体験の郷」、霜降り肉の「倉石牛」などの特産品が登場し、村おこしも盛んで多少はにぎやかになったが、当時は人口4000人、食堂もスナックもない、あるのは農協と郵便局だけという過疎地だった。
1人の青年にとつて、その環境は過酷すぎた。普通の診療所だと外来のみで、夕方になるとどこかに遊びに行ったりできるのだが、1人でも入院患者がいる限りそれもままならない。医師が1人で、24時間体制という非常に厳しい環境条件下にあり、また医学的なことを話せる同僚の若い医師もいなかった。唯一の楽しみといえば、週1回、五戸病院へ外科研修に行くことだった。
「東北大学の医学部に行った連中は、虫垂炎や胃の手術をしているというのに、おれは田舎の診療所でじいちゃん、ばあちやんの脈や血圧を計るだけで日々が過ぎていくのか」
明秀は無性に焦りを感じそれが強いストレスとなり、5月に入ってから突然、左耳が聞こえなくなり、五戸病院の耳鼻科で診てもらうと突発性難聴と診断される。さらに下痢が止まらなくなった。

三戸郡倉石村の診療所ではたった一人で患者の診療に当っていた明秀
環境の変化と疎外感は、タフで明朗快活な青年の精神と肉体に影響を与え、さらにこの診療所で、明秀は痛苦を味わうことになるのである。
診療所の事務長が検診で胃のX線を撮ったが、そこに進行性がんがあったのを明秀は見落としていたのだ。半年後、事務長が貧血を起こして八戸市内の病院に入院したところ、進行性がんであることが判明。緊急に手術は行われたが、再発してまもなく死亡した。
事務長の家族は若い3年目の医師を責めたりはしなかったが、明秀としては医学的技術の不足を痛感した。単純な見落としである。しかも、あとでそのフィルムを11回見せられてもどこにがんがあるのかわからなかったほど、医療レベルは低かった。
「自分をかばうわけではないですが、そういう未熟な人間を診療所に派遣しなければならないような厳しい青森県の事情なんだなと思いました。青森県立中央病院でも研修はしましたが、1人でするような医療は誰も教えてくれませんでした。大病院の中にいると、ほとんど責任の所在がはっきりしないので、いい加減で手抜きも覚えますし、そういったこともよくなかったと思います。必ず上司がいて2人でやっているような診療所だったならば、状況は変わっていたと思います」
たとえ、研修を終えたばかりの医師であろうと、倉石村の患者にとって明秀は信頼すべき「お医者さん」である。
医師としての腕が未熟でも、診療所にやってくる患者すべての病気を診なければならない。しかし、へき地の診療所に医師が1人という体制を変えていかないかぎり、ミスが起きる可能性は大きい。明秀の言葉は、実は日本の医療の現実をとらえてもいるのである。
明秀が卒業した自治医大の建学の精神は、「へき地・地域医療に挺身する気概と情熱に富んだ医師を育てる」というのが目的である。明秀も6年間の大学生活と2年間の研修を終え、ヨ般の私立大学や国立大学出身者にはできないことをわれわれはへき地において実践する」という気概があったのだ。
倉石村の診療所では、1人でなんでもこなさなければならず、患者と接した現場からさまざまなことを学んだ。公務員の給料で、「当直は毎日だが手当てはゼロ」という厳しい条件のうえ、極度のストレスで身体をこわしたり、医療ミスを犯したりと、明秀はすっかりうつ病のような状態に陥ってしまった。このとき優しくしてくれたのが、のちに結婚することになる県立中央病院で助産師をしていた女性だった。
「とにかく、倉石村には話し相手がいなかった。人間にとって話す相手がいるということは基本的なことですよね。このままだとおかしくなるというときに、女房は、よく訪ねてきてくれました」
現在の明秀からは想像もつかないのだが、たった1人、初めてへき地の診療所で患者を診なければならなかった日々、医師としての責務を果たすべき強い精神力を試され、また鍛えられたのであろう。
次回に続きます…
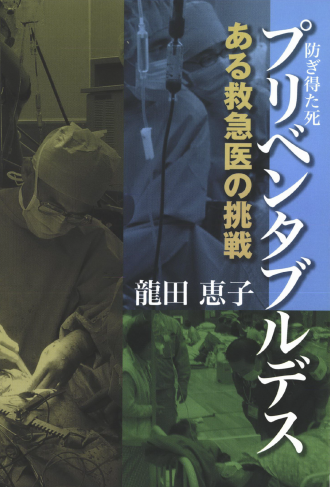 本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。 なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。
本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。 なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。
早く続きを読みたい、書籍で読みたいという方は http://www.cbr-pub.com/book/003.htmlや Amazonから購入できます。
