救急現場、密着ドキュメント!③ 【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】
第1章 こちら救命救急センター
救急現場、密着ドキュメント!③
患者が処置台に移されると、二人の看護師が着衣を脱がせ、ズボンは手早くハサミで切って裸にする。気道確保、心電図の準備がされ、心臓マッサージが続けられる。明秀は患者の妻に、「ご主人はすでに心肺停止で蘇生は難しい状態ですが、全力を尽くします」と告げる。妻はいったん処置室から出ていった。
処置台の患者の身体は微動だにせず、顔は血の気がなく土色だ。心臓マッサージ、電気ショックが施されたが、患者が息を吹き返すことはなかった。
午後十一時二十五分、明秀は患者が死亡したと判断し、すぐに家族が処置室に呼ばれた。
「最善を尽くして蘇生の処置にあたりましたが、残念ながらご主人は亡くなりました」
すでに覚悟していた妻のそばで、急な知らせを聞いてやってきた夫の両親が泣き崩れた。それはまるでテレビドラマのワンシーンのようで、現実の出来事とは思われなかったにもかかわらず、私はつい涙ぐんでしまった。
処置室を出て、廊下の長椅子に腰をおろした。ふと、気づくとそばにはさきほど流産の処置を受けていたスリランカ女性の夫が座っていた。私は腰を上げ、薄暗い外来ロビーヘ向かった。ロビーを一回りしてから、緑の植物があるほうへ歩いた。円形の椅子に腰を下ろしてぼんやりとしていた。緊張がほぐれたのか、少しばかり疲れを感じた。
私は過去に三度、救急車で病院に搬送されたことがある。一度目はある晩秋の夜八時ころから札幌のホテルに入っている飲食店で知人五人と酒を含めた会食をしていた一時間後、急に気分が悪くなり、ホテル内のトイレで嘔吐したが、そのあとの記憶がない。私がなかなか戻ってこないので心配した知人たちが探しに行くと、女子トイレの出入り口あたりで倒れていて(そこまでは自力で歩けたらしい)、誰かが救急車の手配をしてくれたのだろう。私は知人二人に付き添われて夜問急病センターに搬送された。
目が覚めたのと同時にストレッチャーから落ちて、ようやく腕の点滴に気がつき、そこが病院だと知った。そばの椅子で寝ていた知人の一人が、ストレッチャーに上がるのを手伝ってくれた。知人から事の顛末を聞いて驚いた。
「迷惑かけてすみません。もう、大丈夫ですから、どうぞ引き取ってください」
二人に礼を述べた。それが午前四時である。彼らが引き上げたあと、再びストレッチャーの上で朝が来るまで眠った。一泊人院のタクシー帰宅だった。
私には倒れた原因がわからない。日本酒は猪日に三杯程度で、急性アルコール中毒ではなかった。ただ、知人が牡蛎の酢の物を食べていたことを病院に説明したためか、診断書には牡蛎に当たったことが書かれていたらしい。
二度目に救急車で搬送されたのは、日中に地下鉄赤坂見附駅のホームで倒れたときのこと。
意識はあったので、救急隊員に「名前は?」「年齢は?」と聞かれても答えることはできた。赤坂の病院では、過労と栄養不良などと診断され点滴をしてもらい、四時間後にタクシー帰宅した。
いま思えば、私の場合はおそらく救急車を呼ばなくてもすんだような軽症患者で周囲を巻き込んでしまったが、私の母は同じ年に三度、救急車で搬送され、そのまま入院した。
一度目は二月で、心臓が苦しくなって循環器病院に搬送された。発作性心房細動と診断され一カ月近くの入院となった。さらに十月、今度は脳血栓だった。母は倒れる二週間前に肋骨を折って以来、強度のストレスに見舞われ体調がすぐれず、食欲もなかったらしい。寝たり起きたりの状態が続いていたが、その朝は起きたときに物が二重に見えたという。「それはきっとめまいだから寝ていたらいいよ」と父に言われ、そのまま蒲団に入った。このとき父は襖を半分ほど開け、隣の部屋で新聞を読み始めた。五分ぐらいすると、普段からほとんどいびきをかかない母が大きないびきをかきはじめたので、父は驚きすぐに呼びかけた。しかし、まったく応答がないので「これはただごとではない」と異常に気づき、すぐにかかりつけの病院に連絡して症状を告げたところ「うちでは手におえないので、こちらから麻生脳神経外科病院に連絡入れて救急車をそちらに行かせます」という早い判断だった。救急隊が来て、酸素マスクを当てられて車内へ。自宅から約七分で到着した病院の正面玄関で待機していた副院長が「きょうは何日かわかりますか?」と問いかけると、母は意識が戻ったのか小さな声で「十月二十六日」と正確に答えたという。
「よし、大丈夫だ。急いでCTだ」
最初は右半身に麻痺があったらしく、顔の右半分が動かなかったことを父はひどく気にしたのだが、二日後のカテーテル検査の日に私が東京から帰って母の顔を見たときには「麻痺はなくなる。大丈夫」と確信した。ひととおりの検査が終わり、医師に「まだまだ脳が若いです」といわれた母は「生きていてよかった。命を大切にしよう」と涙がこみあげてきたそうだ。麻痺の症状は一週間ほどで消え、後遺症もなく一カ月後に退院した。母の場合はかかりつけの病院長の判断で病院を指定し、迅速に救急車で搬送された。いわゆるそこは救命救急センターではなかったが、救急患者を随時受け付ける脳神経外科病院で周辺医療施設との連携もあり、母は助かっている。
ピーポー、ピーポーとサイレン音を鳴らして救急車が目の前を通過していくのを見るたびに、私は他人事ではないなと思う。
次回に続きます…
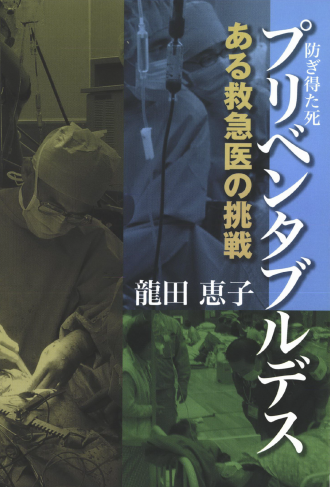 本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。
本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。
なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。
早く続きを読みたい、書籍で読みたいという方は
http://www.cbr-pub.com/book/003.htmlや
Amazonから購入できます。
